サイバーセキュリティとは、脅威アクターからシステム、ネットワーク、プログラムを保護する実践です。攻撃対象領域を理解し、その影響を軽減することが最も重要です。攻撃対象領域とは、特定のコンピューティングデバイスやネットワークにおいて、攻撃者が攻撃できるさまざまな侵入ポイント(表面)の総称です。技術の進歩に伴い、これらの侵入ポイントも増加し、その保護は困難になっています。
現代の組織は、数多くの異なるシステムが連携して機能することに依存しています。クラウドプラットフォーム、リモート従業員、接続デバイス(IoT)に依存しているのです。新たなシステムやデバイスが追加されるたびに攻撃対象領域は拡大します。組織は攻撃対象領域の可視化を通じて、これらのリスクを可視化し管理できます。これにより、管理すべき対象と、それらの管理脅威の潜在的な発生源を理解することが可能になります。
本ブログでは、攻撃対象領域の定義、攻撃対象領域の種類、可視化の重要性、およびその実現方法について解説します。また、攻撃対象領域の可視性を高めるのに役立つ様々なツールについても探求します。
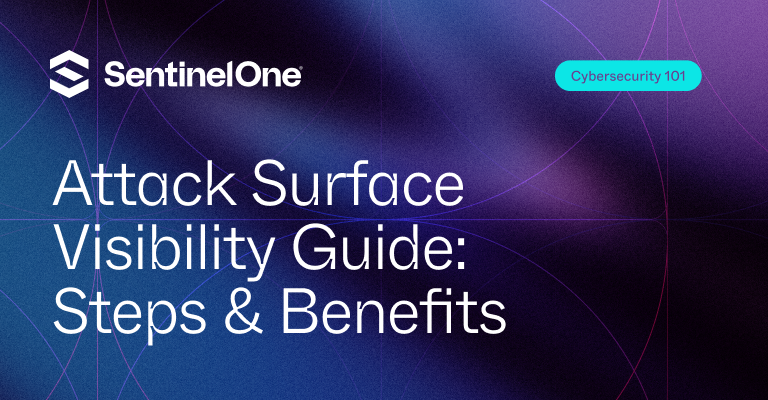
攻撃対象領域の可視化とは?
攻撃対象領域の可視化により、組織は自社のシステムとその攻撃対象領域を構成するすべての稼働コンポーネントを把握・理解できます。これは、すべてのシステム、デバイス、アプリケーションを把握し、何が悪用される可能性があるか、どのような通信経路が存在するかを理解することを意味します。可視化は単なる資産リスト以上のものです。これには、そのような資産の使用状況、所在場所、および潜在的な脆弱性の監視も含まれます。
このプロセスには、攻撃対象領域に関する情報を収集するためのツールや技術の使用が含まれます。このデータはその後、セキュリティチームによってリスク分析されます。これには、ネットワーク上に新しいデバイスが出現したり、ソフトウェアが更新されたりといった時間ベースの監視も含まれます。可視性により、組織は攻撃者が脆弱性を発見・悪用する前に対処できます。
攻撃対象領域の可視性が不可欠な理由
攻撃対象領域の可視性は、脅威に対して組織が先手を打つ能力と固有の要件への対応を可能にします。
可視性はリスク低減の第一歩です。システムやデバイスを可視化することで、セキュリティチームは問題点を確認できます。攻撃対象領域全体を把握することで、更新が必要なソフトウェアや開放されたネットワークポートといった問題に対処可能となり、侵害リスクを最小限に抑えられます。
サイバーセキュリティ規制は業界によって異なります。GDPR、HIPAA、PCI DSSなどの多くの基準では、組織がシステムだけでなくデータも保護することが求められます。攻撃対象領域の可視化を活用することで、これらの規則を満たすことが可能です。可視化ツールは資産、脆弱性、セキュリティ態勢を報告します。これにより監査パスが簡素化され、コンプライアンスが実証されます。
ゼロトラストは、システムやユーザーが本質的に安全ではないという前提に基づいたセキュリティモデルです。つまり、その発信元にかかわらず、アクセス要求をすべてチェックすることを意味します。チームは、厳格なアクセス制御を実施し、行動を監視するために、すべてを見渡せる必要があります。
攻撃対象領域の可視化の構成要素
攻撃対象領域全体の可視性は、より広範な一連の構成要素が連携して機能することに依存しています。これらの要素により、組織は攻撃対象領域を可視化し制御することが可能になります。
資産発見
使用中のすべてのシステム、デバイス、ソフトウェアを特定します。セキュリティチームは、存在すら知らないものを保護することはできません。これにはサーバー、ノートパソコン、クラウドアカウントから、カメラなどの IoT デバイスまで、あらゆるものが含まれます。可視性は監視対象の認識に基づきますが、これは資産発見によって実現されます。
継続的モニタリング
継続的監視は、時間の経過に伴う攻撃対象領域の変化を警告します。新たにインストールされたソフトウェア、接続されたデバイス、変更された設定など、日々変化する資産を監視する必要があります。監視ツールはこれらの変化を追跡し、リスクについてチームに通知します。可視性は一度きりの作業ではなく、継続的なプロセスです。問題が発生した時点で特定するのに役立ちます。
脆弱性管理
脆弱性管理とは、資産内の脆弱性を特定し修正するプロセスです。脆弱性とは、攻撃者に悪用される可能性のある弱点(例:古いソフトウェアや適用されていないパッチ)を指します。可視化ツールはシステムをスキャンしてこれらの問題を検出し、深刻度に基づいてランク付けします。チームはその後、更新プログラムやその他の修正手段を展開できます。
サードパーティリスク管理
サードパーティリスク管理とは、外部ベンダーやパートナー組織に起因するリスクを指します。多くの組織は、外部調達ソフトウェア、クラウドサービス、さらには請負業者に依存しています。これらのサードパーティのいずれかにセキュリティ上の問題があると、攻撃対象領域に影響を及ぼす可能性があります。可視化ツールは、これらの連携関係を調査し、セキュリティ基準に準拠しているかどうかを判断します。
設定ミス検出
設定ミスとは、システムやアプリケーションの設定誤りに起因する問題です。開放されたポート、脆弱なパスワード、暗号化されていないデータなどは、資産を攻撃対象として晒す脆弱な箇所です。可視化ツールは設定をセキュリティルールと照合し、問題を報告します。
拡大する攻撃対象領域を悪用する一般的な脅威
攻撃対象領域が拡大すれば、攻撃者にとって攻撃の機会が増えるだけです。その結果、多くの脅威がこの拡大を悪用します。
マルウェア
マルウェアとは、システムを損傷したり情報を取得したりすることを目的としたソフトウェアです。保護されていないデバイス、パッチが適用されていないソフトウェア、フィッシングメールなどを通じて拡散する可能性があります。複数のエンドポイント(例:ノートパソコンやIoTデバイス)で構成される広い攻撃対象領域では、マルウェアの侵入と拡散が容易になります。
認証情報の窃取
攻撃者はシステムへのアクセス権を得るため、ユーザー名とパスワードを盗みます。脆弱なパスワード、再利用された認証情報、または発見されたアカウントにより、攻撃対象領域は拡大します。侵入後、攻撃者は正当なユーザーを装い機密データにアクセスできます。
フィッシング攻撃
ソーシャル攻撃面は、フィッシング詐欺攻撃によって悪用されます。ハッカーは、従業員を騙してアクセス権を提供させたり、別のものに偽装したマルウェアをダウンロードさせたりします。悪意のあるリンクを1回クリックするだけで、より広範な侵害につながる可能性があります。
設定ミス
設定ミスもよくある脅威です。例としては、公開されたクラウドストレージ、セキュリティ対策が施されていないデータベース、セキュリティ制御の無効化などが挙げられます。広大な攻撃対象領域全体でこうした問題を発見する技術が存在し、それらはデータ窃取や破壊行為のために悪用されます。
攻撃対象領域の可視化のメリット
組織は攻撃対象領域の可視化からメリットを得ます。セキュリティを強化し、ビジネス目標との整合性を高めます。主な利点を以下に示します。
脅威検知
攻撃対象領域全体をチームに可視化することで、リスクをより迅速に特定できます。これらのツールは、悪意ある攻撃者による侵入前に、パッチ未適用のソフトウェアや開放ポートなどの脆弱性を明らかにします。この事前通知により、組織は脆弱性を修正し侵害を防止できます。
ダウンタイムの削減
時に、可視化されていない攻撃対象領域が悪用され、業務を妨害することがあります。脆弱性を特定し保護することで、可視化はこのリスクを軽減します。監視対象のサーバーは、システムを稼働状態に維持するため、マルウェアによる障害が発生しません。
コスト削減
侵害が発生した場合、データ損失、法的費用、修復費用など、そのコストは高額になります。可視性は問題を早期に特定することで、これらのコストを削減します。フィッシングやパスワードクラッキングは、アクセスを得る手段の一つに過ぎません。脆弱性を修正する方が、攻撃からの復旧よりも費用が安い場合が多い。
意思決定
可視性は意思決定の強化にも寄与する。セキュリティチームに資産、リスク、脅威に関するデータを提供する。これによりチームは重要課題を優先化し、システムの安全性を維持できる。管理者は推測ではなく事実に基づいて予算とリソースを計画できます。
顧客の信頼
可視性は顧客やステークホルダーとの信頼関係を構築します。可視性を通じたセキュリティ強化は、組織が保護をいかに真剣に考えているかを示します。これはコンプライアンスと評判の両面で重要です。
攻撃対象領域の完全な可視化を実現するには?
組織は、攻撃対象領域の完全な可視化を実現するために、システム全体の構成要素を可視化し管理する必要があります。
全資産の特定
最初のアクションは、すべてのリソースのリストを作成することです。これは、サーバー、ノートパソコン、クラウドアカウント、サードパーティツールなど、チームが使用するすべてのデバイス、アプリケーション、接続を見つけることを意味します。完全なインベントリを構築するため、ネットワークやクラウド環境をスキャンするツールを自動化します。
継続的モニタリング
次のステップは、継続的モニタリング体制の確立です。新規デバイスの追加、ソフトウェアの更新、ユーザーによる設定変更など、資産は変化します。これらは監視ツールによってリアルタイムで追跡されます。ネットワーク上で新たに開かれたポートや不正なデバイスなど、リスクに関するアラートが送信されます。これにより、攻撃対象領域の最新状況を把握し続けることができます。
脆弱性の評価
次のステップは脆弱性の評価です。資産をスキャンするツールは、このような弱点、最新のソフトウェアの欠如、パッチの適用漏れなどの脆弱性を探します。各脆弱性について、潜在的な悪用の可能性ごとに深刻度スコアが割り当てられます。
サードパーティのリスク管理
組織は、ソフトウェアやサービスの提供をベンダーに依存しており、これらは追加の攻撃対象領域となります。チームはベンダーのセキュリティ(サーバー構成やデータ管理など)を検証する必要があります。これらの外部リンクを監視し問題を報告するツールが存在します。契約書にはベンダーがセキュリティ基準を遵守することを明記すべきです。
設定ミスの修正
最後に、設定ミスへの対応でプロセスは完結します。チームはクラウドストレージ、データベース、ファイアウォールをスキャンし潜在的なエラーを検出します。自動化ツールが設定をセキュリティルールと比較し、それに基づいて変更を加えます。ミスが再発しないよう定期的なチェックが重要です。
攻撃対象領域の可視性維持における課題
組織がシステムの可視性を維持するには、いくつかの課題に対処する必要があります。その一部を見ていきましょう。
資産インベントリの不足
すべてのデバイス、ソフトウェア、接続を可視化できなければ、チームはそれらを監視できません。組織には、古いサーバーや忘れ去られたクラウドアカウントなど、表に出てこない資産が存在する可能性があります。これは、組織が急成長した場合や、すべてを追跡する監視体制がない場合に起こります。インベントリの不備は、攻撃対象領域の一部を無防備な状態にします。
シャドーITと不正デバイス
課題の一部は、シャドーIT(IT部門の承認や関与なしに部門がITを利用すること)や不正デバイス(許可されていないハードウェア)です。従業員が個人用クラウドストレージなど、承認されていないソフトウェアやサービスを使用する場合がこれに該当します。これらのデバイスはセキュリティ監視の網を逃れ、攻撃対象領域を拡大します。
クラウドおよびマルチクラウドの複雑性
クラウドおよびマルチクラウド環境の可視性を確保することは、これまで以上に困難になっています。AWS、Azure、Google Cloudは、各組織が異なるシステムやルールで利用する代表的なクラウドサービスプロバイダーの一部です。したがって、仮想マシンやデータベースなど、追跡すべきリソースがそれぞれ存在します。クラウドの設定ミスや忘れられたリソースはリスクを高めます。異なるプラットフォームを管理するには、より多くの時間とツールが必要となります。
サードパーティ依存関係
もう一つの障壁はサードパーティ依存関係です。ベンダーやパートナーが組織のシステムに接続することで、攻撃対象領域に追加の負担が生じます。ベンダーのセキュリティ対策が不十分(例:パッチ未適用のサーバー)な場合、それがリスク要因となります。特に無数のパートナーにフラグが立てられている状況では、これを追跡することは困難です。可視化ツールも内部システムを超えて展開する必要があるため、すべての組織がこれを容易に実現できるわけではありません。
予算とリソースの制約
多くのチームの予算とリソースは、可視化努力を許容可能なペースで展開することを単純に妨げます。これらの問題をスキャン、監視、修正するツールは存在しますが、それらは有料です。組織はまた、これらのツールを運用する熟練したスタッフを必要とします。
攻撃対象領域の可視性を高めるためのベストプラクティス
攻撃対象領域の可視性を高めるには具体的な行動が必要です。組織は特定の方法を用いて、システムをより効果的に可視化し保護できます。
自動化された資産発見
自動化された資産発見は、組織内の全システムとデバイスを特定します。大規模ネットワークでは、手動追跡では見落としが生じやすいです。さまざまなツールがネットワーク、クラウドホスティング、エンドポイントを分析し、あらゆる資産を特定します。
強力なアクセス制御
アクセス制御はシステムにアクセスできる者を制限し、堅牢なアクセス制御が侵入の主な障壁となります。開放されたり脆弱なアクセスは攻撃対象領域を拡大します。パスワード、多要素認証、および役割ベースのルールをチームに推奨します。
定期的なセキュリティ評価
セキュリティを継続的に評価することで、攻撃対象領域が制御不能に拡大するのを防ぎます。これらの評価では、システム内の脆弱性(古いソフトウェアやフィルタリングされていない開放ポートなど)を探します。チームはツールを使用してネットワークやクラウド環境をスキャンし、結果を確認できます。これにより新たなリスクも捕捉できるため、定期的な実施が重要です。
継続的脅威露出管理(CTEM)
CTEM(継続的脅威エクスポージャー管理)は、さらに一歩進んで、より高い可視性を提供します。これは、リスクを観察、評価、対処する継続的なプロセスです。CTEMツールは、攻撃対象領域と同様に脅威(マルウェア、データ漏洩など)を追跡し、危険度の優先順位付けを行います。そこから、チームはサーバーへのパッチ適用や脆弱なアカウントのロックダウンなど、最も深刻な脅威を優先的に対処します。CTEMは攻撃の速度に対応するため、常時稼働しています(単発のスキャンとは異なります)。
結論
現代のサイバーセキュリティフレームワークには、攻撃対象領域の可視化が不可欠です。組織が自らを守るために攻撃対象領域、その種類、構成要素、脅威に関する認識に依存するにつれ、可視性はリスクを軽減し、ポリシーを適用し、ゼロトラストを支援します。その後、資産を発見し、追跡し、脆弱性やバグなどの問題を修正します。大規模な攻撃対象領域の可視性は、マルウェア、フィッシング、エクスプロイトなどの脅威を阻止するために不可欠です。
組織は資産のスキャンとアクセス制御によってこれを実現できます。攻撃対象領域の可視化には独自の課題(シャドーITや予算問題など)がありますが、自動化や評価の実施といったベストプラクティスは有効です。
次のステップは、継続的モニタリング体制の確立です。新規デバイスの追加、ソフトウェアの更新、ユーザーによる設定変更など、資産は変化します。これらは監視ツールによってリアルタイムで追跡されます。ネットワーク上で新たに開かれたポートや不正なデバイスなど、リスクに関するアラートが送信されます。これにより、攻撃対象領域の最新状況を把握し続けることができます。
FAQs
攻撃対象領域とは、攻撃者がシステムに侵入するために利用可能なすべての接点の総称です。サーバーやノートパソコンなどのデバイス、ソフトウェアアプリケーションやオペレーティングシステム、ポートやWi-Fiなどのネットワーク接続が含まれます。また、ユーザーアカウントやパスワードも対象となります。
組織は攻撃対象領域の隅々まで可視化し把握できる必要があります。具体的には、存在するシステム・デバイス・接続の全容とそのセキュリティ状態を理解することです。資産の特定、脆弱性スキャン、新規デバイスの追加やソフトウェア更新などのイベント監視などが含まれます。
組織は、パッチ適用済みのシステム、厳格なアクセス制御、および重要な資産を保護する環境を確保するための分離ネットワークを採用することで、リスクの可能性を低減できます。継続的なリスク評価や従業員のトレーニングといった積極的なセキュリティ対策も、露出の機会を減らします。
現代のCISOにとって、敵対者が発見・悪用する前に未知の脆弱性を発見・修正するには、深い可視性が不可欠です。この知見により、セキュリティ投資の優先順位付けが可能となり、あらゆるデジタル資産にわたる新たな脅威に対してはるかに迅速に対応できます。
組織は、リアルタイム可視化システム、継続的資産発見システム、脅威インテリジェンスプラットフォームをセキュリティアーキテクチャに統合できます。この予防的な手法により、既知および未知の脆弱性について組織がリアルタイムで把握できるようになります。
自動化は、広範かつ複雑な企業環境全体における脆弱性の検出、分析、修復プロセスを加速・自動化できるため、このアプローチの中核的な推進要因です。自動化システムは人的ミスを最小限に抑え、対応時間を短縮することで、より効率的で統一されたセキュリティ手順を確立します。
可視性は、クラウド環境の変化によってさらに複雑化します。組織は、動的で多数のプラットフォームに分散したリソースを監視する必要があります。堅牢な クラウドセキュリティソリューション は、クラウド資産の集中管理と継続的な監視を提供することで、業界全体にわたる可視性を実現します。
ハイブリッド環境やマルチクラウドを含むIT環境の急速な進化により、顧客は不完全な資産インベントリや監視の死角を抱えることが多くなっています。さらに、検出されないまま残るデータが膨大であり、潜在的な設定ミスも多いため、継続的な監視と効果的な脅威検知が困難です。


