本記事では、サイバーセキュリティ戦略の必要性、策定方法、構成要素、および大企業向け戦略と中小企業向け戦略の違いについて概説します。
 サイバーセキュリティ戦略とは?
サイバーセキュリティ戦略とは?
サイバーセキュリティ戦略の正式な定義は、組織、政府、または個人が、情報技術(IT)システム、ネットワーク、データ、資産をサイバー脅威から保護するために従う体系的なアプローチです。リスク管理、システムの完全性の確保、潜在的なサイバー攻撃から機密データを保護するために不可欠です。&
なぜ必要なのか?
企業や個人のデジタルプラットフォームへの移行は数年前から進行しており、パンデミック時の制限により加速されました。実店舗への来客減少の影響を相殺するため、企業は迅速に電子商取引へ移行し、自動化によって運営コストを削減しました。システムやデータのクラウド移行も進められ、リモートワークが導入されました。
個人ユーザーもeコマースやソーシャルメディアを積極的に活用し、スマートデバイスを用いていつでもどこでも商業・私的目的に利用し、リモートワークを行うようになりました。
これらの動きはネットワークインフラの大幅な増強をもたらし、公共空間におけるWi-Fiベースのネットワークへのアクセスが爆発的に増加した。残念ながら、この動きは深刻なセキュリティ問題を引き起こしたが、組織や個人は直ちに対処しなかった。サイバーセキュリティ防御の発展は、新たなサイバー脅威を用いてシステム、ネットワーク、データ、資産への攻撃を開始するハッカーに遅れを取った。
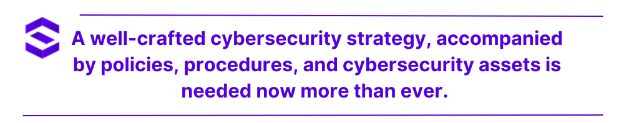 ランサムウェアは企業にとって深刻な脅威となり、個人にとってはID盗難のリスクをもたらしました。幸い、サイバーセキュリティは急速に進化し、戦略的な対策の実施により報告されるインシデント数は大幅に減少しています。
ランサムウェアは企業にとって深刻な脅威となり、個人にとってはID盗難のリスクをもたらしました。幸い、サイバーセキュリティは急速に進化し、戦略的な対策の実施により報告されるインシデント数は大幅に減少しています。
しかし、新たな脅威は日々出現し、悪意ある行為や偶発的なミスが原因で、金銭的損失や評判の毀損につながるインシデントは依然として発生しています。
今こそ、ポリシー、手順、サイバーセキュリティ資産を伴った、周到に練られたサイバーセキュリティ戦略が必要とされています。
サイバーセキュリティ戦略の主要構成要素
明確に定義されたサイバーセキュリティ戦略には通常、いくつかの主要な構成要素が含まれます。以下に10の要素を示します:
1. リスク評価
- 資産の特定:保護が必要な重要なシステム、データ、資産を理解する。
- 脅威の特定:脅威の種類(例:マルウェア、フィッシング、ランサムウェア、内部脅威)に対して組織が脆弱である点を特定する。
- リスク評価:これらの脅威が組織に及ぼす可能性と影響を評価する。
2. セキュリティポリシーと手順
- セキュリティ対策の実施方法と維持方法を定義する正式なセキュリティポリシーを策定する。
- 侵害やサイバー攻撃に対処するためのインシデント対応手順を確立する。
- ポリシーが 規制および業界のコンプライアンス要件(例:GDPR、HIPAA)に準拠していることを確認する。
3. 技術とツール
- ファイアウォールと侵入検知システム(IDS/IPS):境界セキュリティを導入し、不審なトラフィックを監視・遮断する。
- 暗号化:強力な暗号化アルゴリズムを使用して、保存時および転送中のデータを保護します。
- アクセス制御とID管理:多要素認証と役割ベースのアクセス制御を通じて、許可されたユーザーのみが機密システムやデータにアクセスできるようにします。
- マルウェア対策とエンドポイントセキュリティ:エンドポイントデバイス上のマルウェアや不審な活動を防止・検出するツールを使用します。&
4. セキュリティ意識向上とトレーニング
- 従業員トレーニング:従業員向けに、セキュリティのベストプラクティスやフィッシング攻撃などの潜在的なサイバー脅威の認識に関する定期的なトレーニングを実施します。
- セキュリティ文化:組織内の全員がセキュリティを最優先事項とする、サイバーセキュリティ意識の高い文化を醸成する。
5. 監視と検知
- ネットワークトラフィック、ログ、ユーザー活動を追跡・分析する継続的監視システムを導入する。
- セキュリティ情報イベント管理(SIEM) ツールを使用して、異常、セキュリティイベント、侵害をリアルタイムで検出します。
6.インシデント対応と復旧
- サイバーインシデント発生時に取るべき行動(コミュニケーション戦略や封じ込め措置など)をまとめたインシデント対応計画を作成する。
- 侵害や攻撃発生後にシステムとデータを迅速に復旧し、ダウンタイムと損失を最小限に抑えるための災害復旧計画を策定する。
7.コンプライアンスと法的考慮事項
- データ保護法や業界固有の基準など、必要な法的・規制要件を満たすサイバーセキュリティ戦略を確保する。
- コンプライアンスを検証し、必要に応じてポリシーを更新するための定期的な監査を実施してください。
8. 定期的なテストと更新
- システムの弱点を特定するための定期的な脆弱性評価と侵入テストを実施してください。
- パッチ管理:既知の脆弱性から保護するため、ソフトウェアとシステムを定期的に更新する。
- 新たな脅威や技術が出現するにつれ、サイバーセキュリティ戦略を継続的に見直し改善する。
9. 連携と情報共有
- 他の組織やサイバーセキュリティコミュニティと連携し、新たな脅威やベストプラクティスに関する情報を共有する。
- 脅威インテリジェンスネットワークに参加し、新たなリスクに先手を打つ。
10. ガバナンスとリーダーシップの支援
- 経営陣の支持を得て、サイバーセキュリティがリーダーシップレベルで優先されるようにする。
- サイバーセキュリティガバナンスフレームワークを確立し、組織全体におけるサイバーセキュリティ活動の役割、責任、説明責任を割り当てる。これらの要素に取り組むことで、サイバーセキュリティ戦略は組織がリスクを軽減し、サイバー攻撃の影響を低減し、事業継続を確保するのに役立つ。
サイバーセキュリティ戦略の策定
サイバーセキュリティ戦略の策定は、他のビジネス戦略の策定と本質的に変わりません。基本的な4つの段階があります:
- 特定と評価
- 目的と目標の設定;
- 成功基準と測定指標の定義;&
- 保護が必要な資産(例:金融システムやデータ)と必要な保護レベルを特定する;
- 既知の脆弱性と、それらを悪用する潜在的な脅威を特定する;
- 各脅威に確率と影響度を割り当て、脅威カテゴリーを作成する。
- 対策の特定
- 市販ソフトウェアソリューションの評価、関連する導入コスト、継続的な費用と便益の分析。これには第三者の関与が想定される。
- リスク軽減・回避戦略の一環として、内部ポリシーと手順の評価・修正。 li>
- リスクと脅威に対処する戦略の策定:
- ロードマップまたは実施計画の策定(以下を含む):
- 人事面での影響、特にリソースの割り当て、トレーニング、および意識向上。これは最も難しい領域となる可能性がある;
- ITおよびその他の分野におけるインフラストラクチャへの影響。例:特定業務領域へのアクセス制御導入
- 戦略を最新状態に保つための継続的活動と必要なリソースの定義。
- ロードマップまたは実施計画の策定(以下を含む):
- 戦略の実行: 上記で定義した戦略を運用に移すための標準的な実施プロジェクト管理活動です。主な活動には以下が含まれます:
- 実施のためのプロジェクト計画;
- 予算とリソースの割り当て;
- 研修と啓発活動を含む人事プログラムの実施;
- インフラストラクチャの変更(例:重要区域へのキーパッドアクセス);および
- ソフトウェア導入;
これは単発の取り組みではありません。サイバー脅威の多様性と新たな脅威の日常的な出現により、継続的な対応が求められます。企業環境では、生産機械の変更やモノのインターネット(IoT)デバイスの導入など、新たなプロセスや手順を検討する際には見直しが必要です。
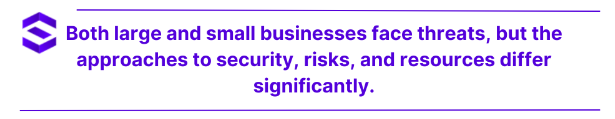 大企業と中小企業のサイバーセキュリティ比較
大企業と中小企業のサイバーセキュリティ比較
大企業と中小企業のサイバーセキュリティにおける基本的な目的と目標は本質的に同じです——システムやデータを侵害する活動による被害の防止です。主な違いは規模にあります。大企業も中小企業も脅威に直面しますが、セキュリティ、リスク、リソースへのアプローチは大きく異なります。大企業と中小企業の間の主な違いと課題を理解することは、それぞれに合わせたサイバーセキュリティ戦略を策定するのに役立ちます。検討すべき8つの項目は以下の通り:
1. リソースの規模
-
大企業:
- 一般的に、大企業は専任のIT・サイバーセキュリティチーム、高度なツール、技術・サイバーセキュリティへの十分な予算を有しています。
- セキュリティオペレーションセンター(SOC)、脅威インテリジェンス、24時間体制の監視といったハイエンドなセキュリティソリューションへの投資が可能です。
-
中小企業:
- 中小企業は、サイバーセキュリティに専念するための資金や専任のITスタッフを欠いていることがよくあります。
- サイバーセキュリティは、一般的なIT担当者が対応するか、外部委託されることがあり、高度な監視や脅威検知機能が制限される可能性があります。&
2. 脅威の種類
-
大企業:
- 大規模組織は、高度持続的脅威(APT)、サプライチェーン攻撃、国家が支援する攻撃など、高度な攻撃の標的となる可能性が高くなります。
- また、標的型分散型サービス妨害(DDoS)攻撃や、企業秘密や知的財産などの貴重な情報を盗むことを目的とした大規模なデータ侵害に直面する可能性もあります。
-
中小企業:
- 中小企業は高度な攻撃の標的となる頻度は低いものの、ランサムウェア、フィッシング、ソーシャルエンジニアリングといった一般的な脅威に対してより脆弱です。&
- サイバー犯罪者は、中小企業が堅牢な防御策を欠いている可能性があり、「容易な標的」と見なされるため、しばしば中小企業を標的にします。
3. リスクと影響
大企業:
- 大企業における侵害の影響は、財務的損失、評判の毀損、規制当局による罰則の可能性という点で深刻なものになる可能性があります。しかし、回復のためのリソースを保有している場合が多く、より迅速な対応が可能です。
- 大企業は、事業分野に応じてGDPR、SOX、HIPAAなど複数の規制に準拠する必要があるため、コンプライアンスリスクが高くなる傾向があります。
-
中小企業:
- 中小企業への攻撃が成功すると壊滅的な打撃となり、財務的影響が深刻すぎる場合、事業の閉鎖につながる可能性があります。
- 中小企業は十分なサイバー保険に加入していない場合があり、攻撃の全費用を負担せざるを得ない脆弱な立場にあります。&
- 評判の毀損も中小企業にとって重大な問題です。信頼の再構築は困難であり、顧客は急速に信頼を失う可能性があります。
4. セキュリティ基盤
-
大企業:
- 大企業は通常、複数のオフィス、クラウド環境、サプライチェーン、場合によってはグローバルな事業展開など、より複雑なITインフラを有しており、攻撃対象領域が拡大します。
- ファイアウォールやエンドポイント検知・対応(EDR)システム、侵入検知システム(IDS)、SIEM、脅威インテリジェンスプラットフォームなどの高度なセキュリティ技術に投資しています。
-
中小企業:
- 中小企業は一般的にインフラが簡素ですが、防御が容易というわけではありません。実際、暗号化、適切なファイアウォール設定、バックアップ戦略といった基本対策が欠如している場合があります。
- 多くの中小企業はGoogle WorkspaceやMicrosoft 365などのクラウドサービスに依存していますが、これらの環境を安全に設定しなければ、クラウド設定ミスなどの攻撃に対して脆弱です。
5. セキュリティ意識とトレーニング
-
大企業の場合:
- 大企業は頻繁なサイバーセキュリティ意識向上トレーニングを実施し、攻撃をシミュレートすることで、従業員が現実の脅威に備えられるようにします。
- 組織の複数レベルでセキュリティ文化を確立し、新入社員から経営幹部まで全従業員が自社の保護における役割を理解できるようにします。
-
中小企業の場合:
- 小規模企業はリソースが限られているため、研修の重要性を見落としがちです。従業員はフィッシング攻撃の識別、パスワード管理の実践、機密データの安全な取り扱いについて十分な研修を受けられない可能性があります。
- セキュリティ意識が低いため、従業員は一般的なソーシャルエンジニアリング攻撃に対してより脆弱になる可能性があります。
6. コンプライアンスと規制
-
大企業:
- コンプライアンスは、PCI-DSS、HIPAA、SOX、およびGDPRなどの枠組みに基づく規制監査や法的義務の対象となる頻度が高いためです。
- これらの規制を確実に遵守するため、多くの場合、社内に法務・コンプライアンス部門を設置しており、遵守に失敗すると多額の罰金が科される可能性があります。
-
中小企業:
- 中小企業は規制要件の対象となるケースが少ないかもしれませんが、医療や金融などの業界では、業界固有の基準への準拠が依然として必要です。
- ただし、コンプライアンスは大企業に比べて優先度が低いと見なされる可能性があり、法的・財務的リスクにつながる恐れがあります。
7. サイバーセキュリティツール
-
大企業向け:
- 大規模組織は包括的な保護を提供するエンタープライズグレードのサイバーセキュリティソリューションに投資できます。これにはエンドポイント保護プラットフォーム、暗号化ツール、多要素認証(MFA)、ネットワークセグメンテーションなどが挙げられます。
- また、脆弱性を特定するための定期的なペネトレーションテストやサイバーセキュリティ脅威シミュレーション(「レッドチーム」演習)の実施も可能です。
-
中小企業:
- 中小企業は、手頃な価格のオールインワンサイバーセキュリティソリューションやマネージドセキュリティサービスプロバイダー(MSSP)に依存することが多い。
- 最先端技術を導入できない場合でも、VPN、マルウェア対策、ファイアウォール、パスワード管理ツールなどの低コストツールでもセキュリティを大幅に向上させられます。
8. インシデント対応と復旧
-
大企業:
- 大企業は通常、攻撃による財務的影響を軽減するため、正式なインシデント対応(IR)チームやサイバーセキュリティ保険を保有しています。
- 侵害や攻撃後も業務を維持できるよう、災害復旧および事業継続計画の演習を頻繁に実施しています。&
-
中小企業:
- 中小企業は体系的なインシデント対応計画を整備している可能性が低い。攻撃が発生した場合、対応が事後対応的になりがちで、予防的対応が取れないため、ダウンタイムが長期化する恐れがある。
- リソース不足によりシステムの迅速な復旧が困難な場合や、長期間の業務中断を許容できないため、復旧に時間がかかる可能性があります。
両者共通の重要考慮事項:
-
大企業:
- 大規模かつ複雑な攻撃対象領域を保護する必要がある。
- 複数の規制のバランスを取り、高いセキュリティ成熟度を維持しなければならない。
-
中小企業:
- より費用対効果が高く、導入が容易なソリューションが必要。
- アウトソーシングを活用し、パッチ適用や基本的な従業員トレーニングといった必須のセキュリティ対策に注力することで効果を得られる。
サイバーセキュリティ戦略で優位に立つ
要約すると、大企業も中小企業も、自社の規模、リスクプロファイル、利用可能なリソースに合ったサイバーセキュリティ戦略を採用する必要があります。大企業はその規模ゆえに高度なソリューションを必要としますが、中小企業は標的型脅威に直面する機会は少ないものの、基本的かつ手頃な防御策が整っていなければ同様に脆弱です。
ニーズの規模に関わらず、SentinelOneがお役に立ちます!
FAQs
簡単に言えば、サイバーセキュリティ戦略とは、組織や個人がデジタル資産、情報システム、データをサイバー脅威から保護するために実施する包括的な計画です。これらの戦略には、サイバー攻撃を防止、検知、対応するための技術、ポリシー、実践の組み合わせが含まれます。
7つのサイバーセキュリティ戦略は、組織がサイバー脅威から防御するための体系的なアプローチを提供するため、政府や業界のフレームワークで頻繁に強調されています。これらの戦略は、オーストラリアサイバーセキュリティセンター(ACSC)やその他のグローバル機関によるものなど、国家安全保障イニシアチブやサイバーセキュリティフレームワークの一部です。
具体的な分類は若干異なる場合がありますが、7つの主要戦略には通常以下が含まれます:
1.アプリケーションのホワイトリスト化
2. アプリケーションのパッチ適用
3. Microsoft Office マクロ設定の構成
4.ユーザーアプリケーションの強化
5. 管理特権の制限
6. オペレーティングシステムのパッチ適用
7. 多要素認証(MFA)
サイバーセキュリティ戦略の策定には、通常3つの基本段階があります:
第一段階:脅威の特定と評価
明確な目的と目標を設定することから始めます。次に、成功を測定するための基準と指標を定義します。財務システムやデータなどの重要な資産を特定し、必要な保護レベルを決定します。次に、既知の脆弱性とそれらを悪用する可能性のある潜在的な脅威を評価します。最後に、これらの脅威に発生確率と影響度を割り当て、分類と優先順位付けを行います。
ステージ2:対策の特定
この段階では、市販ソフトウェアソリューションの評価を行います。導入時のコスト、継続的な運用コスト、およびメリットを考慮し、多くの場合第三者の意見も必要となります。さらに、リスクを軽減し潜在的な脅威を回避するため、内部ポリシーと手順を見直し調整します。
ステージ 3: リスクと脅威に対処する戦略の策定:
最後に、このステージでは、リソースの割り当て、スタッフのトレーニング、および意識向上に焦点を当てた明確なロードマップを作成します。特定の業務エリアへのアクセス制御など、必要なインフラ変更を検討します。戦略を最新かつ効果的な状態に保つために必要な継続的な活動とリソースの概要を示すことが重要です。


